やくPです。
ご覧いただきありがとうございます。
私自身、病院薬剤師の頃はNST担当の薬剤師として、チーム回診への参加はもちろん輸液や栄養の管理、そして処方提案などの業務を担ってきました。
今でこそ、Twitterやインスタで輸液・栄養分野を中心に情報を発信していますが、私がNST担当になってからすぐに前任者が退職されたため自分の力で知識を深めなければいけない環境に、当時はかなり苦労しました。
ではどのようにして自分が輸液、栄養に詳しくなったでしょうか?
それは、輸液・栄養の書籍を数多く読んで、現場で活用してきたからです。
そこで本日は、「NST薬剤師おすすめ 輸液・栄養の書籍“7選”」というテーマでお届けします。
初心者からNST専門療法士を目指す方まで、おすすめできる書籍を紹介しています。
新年度を迎えるこの時期に、輸液・栄養分野の勉強を書籍でも初める後押しになれば幸いです。
日本静脈経腸栄養学会静脈経腸栄養テキストブック
まさに、栄養療法の基礎から応用まで押さえたNST専門療法士の教科書的な本。
著書は一般社団法人日本静脈経腸栄養学会(NSTといえばこの学会)
気になる内容は、解剖から”生理”、”生化”、”経腸栄養”、”静脈栄養”、”各病態における栄養管理”まで幅広く網羅されています。
なんと“約600ページ” とかなりの厚さです。(持ち歩くのはかなり不便…)
基本から細かい内容まで中身はかなり充実しています。
NST専門療法士を目指す方は購入必須の1冊です。
NST栄養療法トレーニングブック
症例を通じて、各疾患での輸液、栄養への具体的な介入が学べます。
薬剤師の視点で栄養管理の内容が書かれている書籍は数少ないため、本書は貴重な1冊です。
気になる内容ですが、消化器疾患からがん、在宅まで幅広い症例での介入事例が紹介されています。
一度は困ったことがあるようなケースに対して、どんな対応して、どういう結果になったかをわかりやすく教えてくれるのですごく役立ちます。
教科書のように抽象的な内容は少ないため、実践にすぐに使える知識がほしいという方にはおすすめです。
レジデントのためのこれだけ輸液
研修医向けの本書ですが、図解と文章の程よいバランスで、他の医療スタッフでも理解しやすいようにまとめられているのが特徴です。
テーマの通り、輸液や電解質を中心に基礎から疾患別の輸液治療まで幅広く学べます。
病院勤務の方は、輸液は見ない日はないと思います。
日常業務と切っても切りはなせないからこそ、輸液を基本から丁寧に押さえる上で長く使える一冊です。
これから輸液を勉強しようと思ったら最初におすすめしたいのは本書ですね。
ただし、本書の内容が輸液中心のため、もし栄養も学びたい方は別の書籍も合わせて買うことをおすすめします。
レジデントのための食事・栄養療法ガイド
先ほどご紹介しました、レジデントのための輸液と同じ「レジデントのための○○」シリーズの1冊です。
本書は、食事・栄養療法の評価から栄養指導、そして栄養管理からみた輸液管理も学ぶことができる1冊です。
先ほどご紹介した「レジデントのためのこれだけ輸液」で電解質、体液コントロールを中心に学び、本書で病態による栄養管理の違いや、静脈・経腸栄養で注意すべき合併症を網羅すれば、薬+栄養管理の視点からも活躍できる薬剤師に成長できるはずです。
薬剤師のための栄養療法管理マニュアル
2023年発売された新書です。
私が輸液栄養を学ぼうと思ったタイミングに発売されていたら、確実に買っている一冊です。
栄養療法の知識がコンパクトにまとめられていて、白衣のポケットなら入ってしまうサイズだから現場でも使いやすいです。
ポケットサイズなのに各疾患の患者さんの「栄養評価」や「介入ポイント」、輸液管理では「投与法」「薬剤との相互作用・配合変化」などにも対応できる優れものです。
凝縮してまとめられている分、文字記載が中心になるので、自宅でじっくり勉強用として使うというよりは、業務中の隙間時間で確認する書籍として活用するのがおすすめです。
一般社団法人日本静脈経腸栄養学会 NST専門療法士認定試験過去問題集
NST専門療法士の試験過去問題集。厳選された問題に加えて、解説がかなり充実しています。
私の経験ですが、最初にご紹介しました「日本静脈経腸栄養学会静脈経腸栄養テキストブック」と本書の2冊でNST専門療法士の試験に合格しました。
難点がひとつありまして、発売日が2016月3月と7年前の書籍のため、新刊が発売される可能性もあるのが悩みどころです。(発売の予定情報2023年6月時点ではありません)
私が試験を受けた際は同じ問題は出ませんでしたが、類似の問題は何問もありました。
NST専門療法士認定試験のレベルをイメージする上でも過去問の把握はかなり重要だと思います。
NST専門療法士認定試験を受ける方は、手元にあった方が良い一冊です。
詳述!学べる・使える 水・電解質・酸塩基平衡異常Q&A事典
題名の通り、水・電解質・酸塩基平衡までQ&A方式で学ぶことができます。
Q&A方式の良いところは1つの質問に対して、回答が2ページほどで終わるので少しの隙間時間からでも読みやすいです。
問題数は175とかなり多いです。
現場で皆さんが遭遇するであろう疑問への回答を、検索して効率良く得ることができるのもメリットです。
問いに対する答えを導き出すためのプロセスも本書を読んでいて勉強になると思います。
最後に
いかがでしたでしょうか?
これから本を買おうと思った方はぜひ参考にしてください。
栄養・輸液領域は、がんなどの治療の変化が著しく分野ではないため、書籍を一度購入すると長いこと現場で活躍してくれると思います。
今後も気になる書籍や実際に購入してよかった書籍を紹介しますので他の投稿もぜひお読みください。
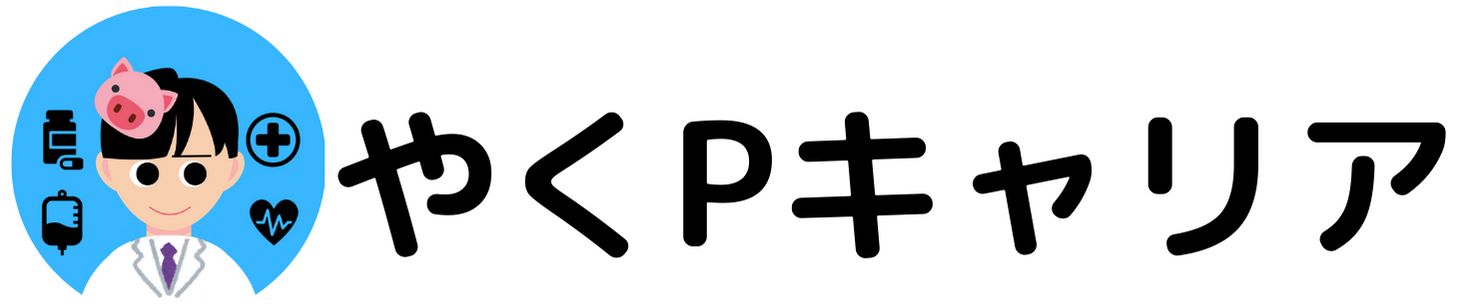










コメント
コメント一覧 (1件)
[…] あわせて読みたい 【NST薬剤師おすすめ】輸液・栄養の書籍“7選” やくPです。ご覧いただきありがとうございます。私自身、病院薬剤師の頃はNST担当の薬剤師として、チーム回診へ […]