 1年目薬剤師
1年目薬剤師薬の知識がなさすぎて困ってます。
勉強したいと思っても、どの本がいいかよくわかりません。
おすすめの書籍を教えてください。
そこで、今回は「新人薬剤師向け 勉強に役立つ!買って良かったおすすめ書籍 ”6選” 」というテーマでご紹介します。
新人薬剤師でない方も、”自分もこの本持ってる”、”この本知らなかった”などの共感や新しい発見があると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
治療薬ハンドブック
薬のポケット辞書といえば、「治療薬ハンドブック」。
添付文書記載の重要な内容が、端的にまとめられています。
病院、薬局実習でお世話になった方も多いのではないでしょうか?
職場に置いてあるケースも多いですが、日々確認した内容をマーカーで線を引くことや、直接メモしたいと思うことも多いはずです。
後でメモしようとするとすぐ忘れるので、1冊持っておくと便利です。
紙の書籍購入で電子版もダウンロードできるので、おすすめです。
薬がみえる
薬学生の就活イベントで配布されることもある「薬がみえる」シリーズ。
ご存じの方も多いとは思いますが、イラストが多く、わかりやすいのが特徴です。
疾患の理解から、治療薬の選択、各治療薬の作用機序や副作用、禁忌などの特長まで一連の流れで把握できるのはとても便利です。薬剤師国家試験の勉強にも役に立ちました。
個人的におすすめの勉強で使う手順を紹介しますが、
この手順を繰り返すことで理解がより深まります。1日1剤だけでも良いです。
大事なのは継続することです。
そうすれば、1年間後には”365剤”の薬に詳しくなり、3年後には”1000剤以上”に詳しくなれます。
薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100
大学で、“薬の使い分け”についてあまり学んでこなかったと思います。
実際の現場ではどうでしょうか?
病院やクリニックから薬の問い合わせがあるのはもちろん、患者さんから薬の違いを聞かれることもしばしば…。
そこでおすすめしたいのが、「薬の比較と使い分け100」
皆さんの疑問にエビデンスを用いて、わかりやすく解説されています。
純粋に薬の比較を知るだけではなく、薬ごとの違いを見分けるための考え方も学べます。
なぜ?どこが違うの?と疑問を持ちながら読む進めることで、より自分の成長に繋がります。
基本的臨床 医学知識
薬剤師が仕事を円滑に進める上で、薬の知識はもちろんのこと、“医学知識” も必要です。
薬剤師は薬を中心に勉強しているため、医学知識の不足を実感することも多いと思います。
ただ、いきなり医師の読む書籍はハードル高いと感じる方もいるかもしれません。
そこで、おすすめするのが「基本的臨床 医学知識」です。
医師ともっと話せるようになるのがコンセプトでつくられた本書。
薬剤師向けに医学をかみ砕いた表現してくれており、1冊で多くの症例から具体的な医学の考え方を学べる良書です。
“医学知識“が身に付けば、医師のカルテ記載がわかる、処方への理解が深まることで患者さんへの服薬指導、
他の医療者とのコミュニケーションにも役立ちます。
今日の治療指針
参考書の中の参考書。
めちゃ分厚くて、高額な書籍なので、こんなの絶対買わない…という方が多いかと思います。
「今日の治療指針」は高いけど、めちゃ勉強になる本です。
私が使っていた経験からお話すると、各疾患に対して処方例が充実しているので、自分が若手薬剤師の頃に処方意図が知りたい時に本書で調べると答えがすぐ見つかります。
自分で買ったの?と思った方がいましたら、安心してください。
職場で購入していたので、自分では買っておりません。
(なので、皆さんの職場の上司に買う提案して職場の経費で買うのもありだと思います)
ちなみに毎年新しいのが更新されます。
もし、少しでも安く手に入れたいと思ったら、 最新版でない本書を中古品で探すのもひとつかと思います。
診療ガイドライン2022-2023
先ほど紹介しました「今日の治療指針」は高くて買えないけどほしいという方へ、値段も少し優しい、おすすめの書籍を紹介します。
それが、「診療ガイドライン2022-2023」です。
分厚くて読むのが大変なガイドラインが疾患毎に数ページにまとめられた本です。
ガイドラインに記載のある内容(診断から治療、処方例まで)が簡潔にまとめてくれています。
値段も1万円ちょっとで “ガイドラインのまとめ本” が手に入るなら、ありだと思います。
実際に購入した感想ですが、薬剤師が日常業務で関わる多くの疾患は、網羅されているので現場で大活躍でした。
忙しい中でガイドラインの記載を確認するのは大変で、本書を活用すれば、短時間で業務中に疾患での治療薬の位置づけを把握することができますし、急な問い合わせで代替薬の処方提案する際などに役立ちました。
また、最新版のガイドラインは有料なことも多いですが、本書なら最新のガイドラインのまとめがのっているので大変便利です。
2年に1度、改定されますので早めにほしい方はすぐに購入でいいと思います。
もし最新版がほしいなら、発売されたタイミングでの購入をおすすめします。
最後に
いかがでしたでしょうか?
“これ知ってる”って本が多かったと思いますが、中には “はじめてみた本” もあったのではないでしょうか?
薬剤師にとって、薬の知識はもちろん重要ですが、早いうちから疾患への理解を深められると、治療薬の位置づけから患者さんの病状をイメージできたり、服薬指導での会話もスムーズにできて共感につながると思います。
日々の仕事は忙しいと思いますが、1日1ページ、1薬剤だけでも継続して自己研鑽することで、自分が思い描く薬剤師へ一歩ずつ近づきます。
その上で、今回ご紹介した書籍は忙しい皆さんをきっと助けてくれるはずです。
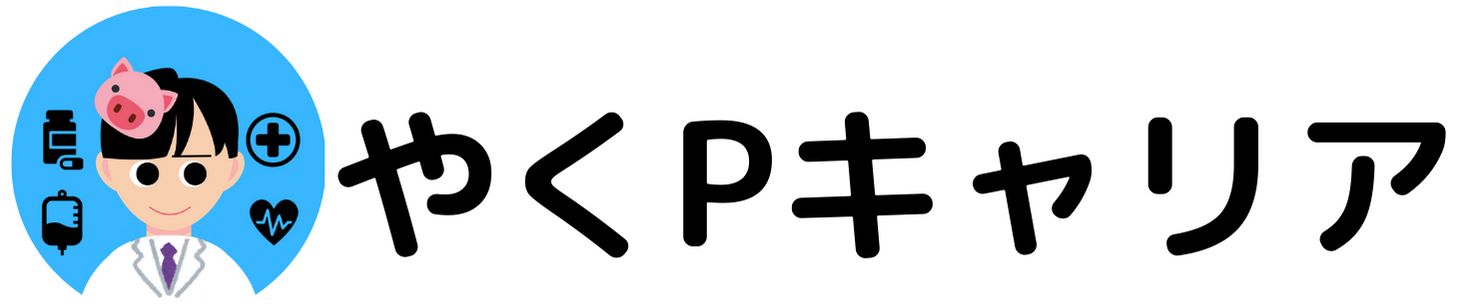












コメント